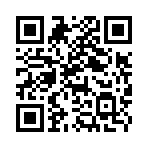2012年10月30日
タマネギ食べちゃった
この子は今頑張ってダイエット中だったのですが、相当お腹がすいていたんでしょうね。
ご存知の方も多いかと思いますが、タマネギもニンニクもワンちゃん・猫ちゃんはダメです。
人間は大丈夫なので不思議な気もしますが、ワンちゃん猫ちゃんの場合、
赤血球という血液の細胞が酸化されてしまい、赤血球が溶けてしまいます。
わかりやすい症状としては赤い尿が出ることが多いですが、
重度の場合、赤血球が壊れひどい貧血が起きることもあります。
治療は輸血が必要な場合には輸血を行いますが、
そこまでひどくない場合には抗酸化薬の投与や、
ネギ類の成分の希釈・代謝・排泄亢進目的で点滴を行うことが多いかと思います。
また食べてしまった直後であれば、
嘔吐させてタマネギを体外へ出す処置を行う場合もあります。
どのくらい食べるとタマネギの影響が出るか、ということですが、
これは一概には言えません。
沢山食べても平気な子も入れば、少し食べただけで症状を出す子もいます。
また犬種的に影響が出やすいこともあるようです。
プルコギを食べてしまったこのワンちゃんは、今のところ問題なく元気いっぱいです。
何事もないといいですね。
ダイエットも頑張ろうね。
2012年10月26日
輪ゴムを飲んじゃった!? 内視鏡検査
元気も食欲もあり一見何の問題もないのですが、レントゲンを撮ってみると、
ご覧の通り。
胃の中に白い輪っかのような紐のような線が見えます(赤丸の中)

これが飲み込んでしまったかも知れないという輪ゴムでした。
実は通常の小さく茶色の輪ゴムくらいでは殆どレントゲンに映らないのですが、
この子が飲み込んだ輪ゴムは大きめの輪ゴムだったため、幸運(?)にもレントゲンに映りました。
レントゲンに映らない場合、飲んだか飲んでないか判断できませんが、
はっきりと映っている以上、飲み込んだのは間違いありません。
最悪の場合は腸閉塞を起こしてしまうことがありますので、処置を行いました。
まず吐かせる処置をしてみましたが、悪心は出るものの吐くことはできませんでした。
(猫ちゃんは普段から吐くことが割とあるかと思いますが、
病院だと緊張してしまい、吐かせる薬を使っても吐かないことが時々あります。
その点、ワンちゃんは吐かせる薬を使うと、病院でもかなりの確率で吐いてくれます。)
吐かせることはできませんでしたので、次なる手段として内視鏡検査を行いました。
内視鏡は胃カメラとも呼ばれる機械ですが、非常に便利な医療機器です。
今までならお腹を開けないと(=手術)わからなかった胃の中の様子がわかり、
またお腹を開けないと取り出せなかった異物も取り出せることが多々あります。
口からカメラを入れますので、人間と違い動物の場合、全身麻酔をかけないと行えませんが、
手術と比べ動物への負担は非常に少ない検査・処置です。
全身麻酔をかけて内視鏡を行っているところです↓

こちらがモニターの画像
やや画像が汚いですが、
左上の茶色のものは消化途中のフード、
右下から右側奥にかけて見える白い紐状のものが飲み込んでしまった輪ゴムです。
このように胃の中がはっきりとわかる点もこの内視鏡の大きな利点です。
輪ゴムはすぐに内視鏡で摘出でき、そのまま麻酔を覚ませて無事処置終了。
夜遅い時間に処置を行ったので、1泊だけ入院になりましたが、
翌日には食事もとり、元気に退院しました。
ちなみに摘出した輪ゴムがこちら
上が摘出した輪ゴムで、下は飼い主さんから参考のためにお借りした同じ輪ゴムです。
胃内の異物を取る手術の場合、胃を切らなければなりませんので、
手術後1〜2日は絶食して入院が必要ですが、内視鏡の場合はその必要がない点が非常に大きなメリットです。
また異物を取る他にも、胃潰瘍や胃のポリープなどの確認もできます。
このように内視鏡検査・処置は非常に便利ですが、
そうは言っても内視鏡検査・処置を行わないで済むにこしたことはないですよね。
病気で内視鏡検査を行わなければならないことは仕方がありませんが、
防ぐことができるような事故のため、内視鏡検査を行わなければならないことは避けてあげたいですね。
(現在当院には内視鏡がありませんので、
内視鏡を行う場合は可能な施設で私が責任を持って行います)
2012年10月24日
臨時休診・診察時間変更のお知らせ
午前は平常通り診察を行います。
11月20日(火曜日)は動物取扱業講習のため、午後の診察を5時からとさせて頂きます。
午前は平常通りです。
ご不便をおかけしますが、ご了承下さい。
2012年10月16日
胃捻転
急にお腹が張ってきて、呼吸も早く元気がない様子とのことでした。
急にお腹が張ってきた場合に怖い病気が胃捻転です。
とくにアイリッシュセッターやアフガンハウンド・スタンダードプードルなどの
胸の深い犬に多い病気で、急激に発症します。
治療をしなかった場合には殆どが半日~1日以内に亡くなってしまうといわれています。
症状としてはお腹が張ってくる、吐きそうで吐けない、といったものが特徴的です。
治療は基本的には手術で胃のねじれを直し、胃を動かないようにお腹の筋肉に固定します。
この電話のあったラブちゃんの場合、
お腹が張ってきているけど吐きそうな様子はないようだったので、
胃捻転ではないかな、と思いましたが、
こちらも飼い主さんも心配ですので、ひとまず診察に来てもらいました。
その結果、とくに大きな問題はありませんでしたので一安心でした。
「大型犬で、食後急にお腹が張ってきて、吐きそうだけど吐けない」
これは典型的な胃捻転の症状です。
必ずしも食後ではありませんが、
胃捻転は一刻を争う重大な疾患ですので、
上記のような症状があった場合、
すぐにかかりつけの動物病院に連絡してみてください。
ちなみに胃捻転のレントゲンがこちら↓
赤い線で囲まれた黒い部分が胃で、黄色の線は捻転ラインといわれるものです。
胃に空気がたまり(空気はレントゲンで黒く映ります)、胃が膨らんでしまっています。
2012年10月10日
肥満細胞腫
最近、立て続けにワンちゃんの肥満細胞腫に遭遇しています。
肥満細胞腫とは、
肥満細胞という細胞が腫瘍化してしまったものです。
もともと体の色んなところに肥満細胞は存在しているのですが、
それが何らかのきっかけで異常増殖してしまいます。
皮膚に発生する場合や、内臓に発生する場合もあります。
ワンちゃんでも猫ちゃんでもこの肥満細胞腫は非常に多く、
皮膚に発生する腫瘍の中で、20%ほどがこの肥満細胞腫だとも言われます。
基本的には悪性腫瘍ですが、
高分化型と言って悪性腫瘍でも比較的穏やかなタイプや、
アレルギーなどの炎症に伴って出現したのかな!?、と思うようなこともあります。
高分化型の場合は何か月、場合によっては年単位で皮膚に肥満細胞腫があるけど、
大きくならない、といったこともありますが、
低分化型というものであれば、早い段階で転移することもあります。
また犬種的には
ラブラドール・レトリバーやシュナウザー、ビーグル
などに多いというデータがありますが、
日本ではとくにパグの子でよく見かけます。
皮膚にできた肥満細胞腫は、
細い針を刺して取れたものを顕微鏡で調べることにより、
容易に診断できることも多い腫瘍です。
顕微鏡で見ると、細胞の中に顆粒がいっぱい見えることが特徴です。
赤い線の内側(薄い紫の部分)が細胞、
黄色い線の内側(濃い紫の部分)が細胞の核、
黄色の線の外側で赤い線の内側が細胞質という部分ですが、
この細胞質内に赤紫の顆粒が存在します。
この写真だと顆粒まではわかりませんが、
なんとなくざらついて見えるかと思います。
このざらついた感じが顆粒なんですね。
肥満細胞腫の治療には、手術や抗がん剤・ステロイド剤などがありますが、
転移がなく皮膚に1つ肥満細胞腫がある場合には、手術での切除が治療の中心になります。
こちらの写真はラブラドール・レトリバーの子ですが、
太ももの裏側に7~8cm程の肥満細胞腫ができてしまいましたので、
手術で取りました。
デキモノは小さなうちに治療したほうが理想的ですので、
もし自宅でワンちゃん・ネコちゃんの体にデキモノがあることに気づいたら、
すぐに主治医の先生に診てもらって下さいね。
なお、もしデキモノがあって肥満細胞腫だと診断がついたら、
そのデキモノにはあまり触らないで下さい。
肥満細胞の顆粒の中には、ヒスタミンという物質が含まれています。
時には触ることによりこのヒスタミンが流れ出てしまうことがあるからです。
この物質は胃を荒らしてしまい、吐き気が出たり胃潰瘍を引き起こしたりします。
(CMでよく見かけるかもしれませんが、ガスターという薬があります。
この薬は胃酸の出過ぎを抑える薬で、H2ブロッカーと呼ばれますが、
実はこのHとは、ヒスタミンのHです。
ヒスタミンが出過ぎてしまうと胃が荒れてしまうんですね)
最後に、時々質問を受けるのが、
「肥満細胞腫っていうことは、うちの子が肥満だからなってしまったんですか?」
という質問です。
これは全く関係ありません。
顕微鏡で見ると、肥満細胞はほかの細胞と比べ
顆粒をたくさん持っていることにより、丸く太って見えるため、
細胞が肥満のように見える、というだけのことです。
決して体全体の肥満とは関係ありませんよ。
痩せている子でも、発生することのある腫瘍です。