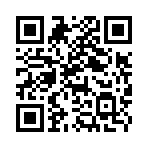2012年09月28日
臨時休診のお知らせ
休診とさせて頂きます。
ご不便をおかけしますが、ご了承ください。
2012年09月28日
尿路結石③
尿路結石でストルバイド結石の次に多いものがシュウ酸カルシウム結石です。
この結石ができてしまうメカニズムはまだ完全には解明されておりませんが、
犬種ではミニチュア・シュナウザー、シーズー、ヨークシャテリアなどに多く発生し、
とくに男の子で多くみられます。
またストルバイトは若いうちから発生することも多い結石ですが、
このシュウ酸カルシウムは高齢のワンちゃんに多い結石です。
猫ちゃんでも比較的よくある結石です。
シュウ酸カルシウム結石はストルバイト結石と比べやや厄介で、
専用の療法食があることはあるのですが、
効き目はあまり期待できないのが現状です。
ですので大きな結石や症状がある場合には、手術で取り除くことになります。
シュウ酸カルシウムは尿pHが酸性になるとできやすくなります。
ビタミンCやビタミンDを与えすぎるとできやすくなります。
シュウ酸の摂取が多すぎてもシュウ酸カルシウム結石ができることがありますが、
通常はあまりないことでしょう。
人間ではほうれん草を生で食べると結石ができやすくなる、といいますが、
これはほうれん草にシュウ酸がたくさん含まれているからです。
最近はシュウ酸の少ない生食用ほうれん草もでていますよね)
ですのでやはりバランスのとれた食事が重要ですが、その他にはなるべく水を飲んでくれることが理想です。この辺りはストルバイト結石と同じです。
しかし、これといった予防法がないことが、
このシュウ酸カルシウム結石の大きな問題点
です。
泌尿器疾患があるとできやすくなりますので、年に1~2回は健康診断を受けてあげて下さい。尿検査だけであれば、尿を持ってきてもらうだけで検査できます。
早期発見で小さな石(結晶)だけであれば、定期的な膀胱洗浄だけで維持できることもありますので、
(膀胱内をきれいな生理食塩水で洗い流し、小さな石(結晶)を取り除きます)
それであれば動物にかかる負担も少なくてすみます。
なるべく早く異常を見つけ早く治療をしてあげることは、
やっぱり大切です。
尿結石に限らずですが、
nbsp;
2012年09月27日
ノミを駆除したのに、ノミがいる?
最近多いノミについての説明に変更させてもらいます。
次回必ずシュウ酸カルシウム結石について書きますので

ノミの寄生や、ノミによる皮膚炎のワンちゃん・ネコちゃんが増えてきています。
ノミは背中に垂らすだけの薬で簡単に予防できますが、
注意しなければいけないのは継続しないと効果がない、ということです。
時々、「先日ノミの駆除をしたけど、まだノミがいるんですが?」
なぜでしょうか?
ノミの一生のサイクルとしては、
カーペットや絨毯などにいるノミが(マユの中に入って待っていることが多い)、
人や動物が通ると、熱や二酸化炭素に反応しマユを破って出てきて、体に付着します。
ノミが体につくと、
①すぐに吸血を開始します。
②吸血開始後、24~48時間で産卵開始。1日に平均で30個ほどの卵を産卵します。
④サナギから孵化したノミはマユの中に潜んでいて、刺激があると人や動物にくっつきます。
という流れになります。
ここで気にして頂きたいのが、③・④の段階です。
卵が地面に落下してから、成虫になるまでに通常は1か月ほどかかります。
ノミは環境が合わない場合にはこのマユの中に入ったノミの段階で、
ノミ駆除薬を使用した場合、体にくっついているノミには非常に即効性がありますが、
すでに環境中にいる、ノミの卵や幼虫・マユはまだ生きているのです。
これらが成長するとまた体に寄生します。
しかし安心してください。
1回薬を使えば、だいたい1か月は効果がありますので、その間はノミがくっついてもすぐに駆除できます。
ただ問題はノミが卵を産めば、またそこからノミが出現しますが、
最近ではノミの卵や幼虫にも効果のある薬が増えてきています。
つまりノミ駆除は
月に1回駆除薬を使用して、体にくっついているノミを駆除する、
幼虫やサナギから成長したノミをまた駆除する・・・、
これを繰り返し、少しずつノミの生活サイクルを絶たせる必要があります。
地道ですが、しかしこれでノミをすべて死滅させることができます。
ただどの程度の期間、続ければいいのでしょうか?ノミは寒く乾燥した時期はサナギから成長しませんので、
静岡であればフィラリア予防薬と同じくらいの期間で
使用してあげればある程度効果はあるのですが、
冬の間でも家の中の湿度が高く暖かいようであれば、
一年中ノミ駆除薬を使用するほうが理想でしょう。
またノミによる痒み・皮膚炎ですが、これはノミアレルギー性皮膚炎といわれるものです。
人間でも蚊に刺されると痒いですよね。
これもアレルギーの一種で、
ノミでも同じような感じではあるのですが、
アレルギーの種類が少し違うため、痒みがしばらくの間継続します。
痒みが強いようであれば痒み止めや、
細菌感染を伴うようであれば抗生剤が必要になります。
さらにノミは瓜実条虫(ウリザネジョウチュウ)という、
必要に応じて検便やこちらの駆虫もしたほうがいいですね。
最後に、環境中のノミの成虫や幼虫・サナギは掃除機で吸い込むだけで殆どが死滅する、
というデータがあります。
ノミの卵に対する効果は不明なようですが、
ご家庭でのノミ対策としては掃除機が非常に有効ですので、
特殊な消毒薬などは使用しなくても、こまめに掃除機をかければノミの駆除が期待できますよ。
2012年09月24日
尿路結石②
先日抜糸を行いました。
体調もすっかり元通りとのことでした。
さて、尿路結石の予防方法や管理方法ですが、
これは結石の種類によって異なります。
結石はその成分により、リン酸アンモニウムマグネシウム(ストルバイト)、
シュウ酸カルシウム、尿酸塩、シリカ、シスチンなどに分類されます。
ただ、そんなこと羅列されてもわかりづらいですよね。
よくある結石としてはストルバイトとシュウ酸カルシウム
という2種類ですので、2回に分けてこの2種類の結石について説明します。
ちなみに今回の話はネコちゃんでも当てはまるものと思ってもらって大丈夫です。
ストルバイトというのは上にも書いた通り、
リン酸アンモニウムマグネシウムが成分の結石です。
この結石は体内のミネラル分(リンやマグネシウムなど)が多すぎたり、
飲水量が少ない場合や長時間トイレを我慢してしまうとできやすくなります。
(尿が濃くなってしまうので結石ができやすくなります)
また尿のpHが高くなる、つまり尿がアルカリ性に傾くと
このストルバイトができやすくなります。
尿のpHは尿中に細菌がいると高くなりやすく、
その他にも食事内容により高くなることもあります。
また体質が関係していることもあります。
ですので、このストルバイトの予防法としては、
なるべく水を飲ませること、
おしっこをあまり我慢させないこと、
バランスの取れたドッグフード・キャットフードを食べさせること、
が重要です。
なるべく水をたくさん飲ませる、というのは難しいですよね。
動物の場合、自分が飲みたくなければ飲まないですもんね・・・。
ただ、最近飲水量を増加させるという、不思議な食器があります。
これを使うと、なぜかたくさん水を飲むようになる子がいます。
水の味が変わるんですかねぇ・・・!?
その他には流れる水が好きな子もいますので、
その場合には市販している水を循環させる食器を
使ってみるのも一つの手かもしれません。
バランスのとれたドッグフードというのはそれほど難しいことではないと思います。
動物病院では療法食といって、尿石症のワンちゃん・ネコちゃん用のフードがありますが
これまで尿石症になったことのない健康な子であれば、
そのようなフードでなくても市販のフードで構いません。
ただし一定以上の品質は保ってあげたいものですが、
幸い尿石症にも配慮したしっかりしたフードがペットショップにも沢山ありますので、
そのようなものであれば構わないでしょう。
過去にストルバイト結石になった・もしくは現在結石治療中の子であれば、
療法食が望ましいです。
療法食はタンパク質・リン・マグネシウムを制限し、
ストルバイトを形成しにくくなっており、
また尿が弱酸性になるようにできていますので、
小さなストルバイト結石であれば、溶けることが期待できます。
再発もほとんどの場合防げます。
ただし、食事管理は基本的に生涯続けることになります。
食事を変えると再発してしまう子が結構多いんですね。
通常は食事管理が中心です。
なお尿中に細菌がいる子であれば、抗生剤をしばらく続ける必要があります。
尿結石を診断するためにはX線検査や超音波検査なども必要ですが、
尿検査でわかることもあります。
自宅や散歩でした尿を液体のまま取って持ってきて頂ければ、
簡易的な尿検査を行えますので、
ご心配な方は尿を取って持ってきて下さい。(取れたばかりの尿が理想ですが・・・)
またとくに尿石症が心配、というわけではなくても
定期的な健康診断は受けさせてあげて下さい。
次回はシュウ酸カルシウムについてお話します。
ご不明な点はお気軽にお尋ねください。
2012年09月19日
休診・診察時間変更のお知らせ
午前は11時30分までの診察とさせて頂きます。
午後は4時~6時までの診察になります。
また9月29日土曜日・9月30日日曜日は学会参加の為、
休診とさせて頂きます。
ご不便をお掛けしますが、ご了承ください。
2012年09月18日
尿路結石
尿の通り道は腎臓→尿管→膀胱→尿道となりますので、
腎臓に結石ができれば腎結石、膀胱にできれば膀胱結石になります。
また尿管や尿道には結石そのものはできにくいですが、
腎臓や膀胱からの結石が流れてきて、
尿管や尿道に詰まってしまうことがあります。
尿管に結石が詰まれば尿管結石、尿道に結石が詰まれば尿道結石といいます。
尿道や尿管が詰まってしまうと大変です。おしっこが出なくなってしまいます。
おしっこは毒素や老廃物を体外へ出すための大事なものですので、
おしっこが出ないと、毒素が体内にたまり、ひどいと尿毒症という、命にかかわる事態になります。
14歳のシュナウザー君、血尿が出てから、おしっこがぽたぽた漏れる様子があり、
腰が立たなくなってしまったということで来院しました。
過去に2回、膀胱結石を取る手術をしているそうです。
今までは膀胱結石が1個ずつだったそうですが、
今回は調べたところ、たくさんの膀胱結石と尿道結石がありました。
(白い粒々としたものが結石です。またこの写真ではわかりづらいのですが、腎臓結石もありました)
恐らく以前からあった膀胱結石が、尿道に流れてはまり込んでしまったのでしょう。
そのためおしっこを十分出せない状態になってしまい、尿が少しずつ漏れるようになってしまったのです。
また痛みも加わり立てなくなってしまったのでしょう。
幸い、尿毒症にまでは至っていませんでした。
治療として、まずおちんちんの先からカテーテル(軟らかい管)を入れて、
その先端を尿道結石の手前まで持っていき、
カテーテルを通して水圧をかけて、尿道の結石を膀胱まで押し戻します。
がっちりと尿道にはまっていたためやや苦労しましたが、
なんとか結石を膀胱まで押し戻すことに成功しました。
その後のレントゲン写真がこちら↓
さっきまで見えていた尿道結石がなくなっています。
もちろん膀胱内に結石があることには変わりませんが、
ひとまずこれで尿は出るようになり、痛みも少なくなります。
膀胱結石の場合、治療法は
①手術で膀胱内の結石をとる (外科的治療)
②食事で溶かしたり管理できる結石であれば、食事療法をする (内科的治療)
に分かれます。
また①の手術の場合、男の子限定ですが、今後尿道に結石が詰まりにくくなるように、
尿道を太く短くする手術(会陰尿道造瘻術:えいんにょうどうぞうろうじゅつ)
を一緒に行うこともあります。
②の内科的な治療は負担は少ないのですが、
溶けない結石や大きな結石などではうまくいきません。
このシュナウザー君の場合、
14歳と高齢ですし、飼い主さんとしては麻酔や手術は避けたいのが当然ですよね。
しかし膀胱結石がとてもたくさんあるため、またすぐに尿道に詰まってしまう可能性や、
結石がうまく溶けたとしても非常に時間がかかり、
その間にもやはり尿道に詰まってしまうことを何回も繰り返すだろうということを考えて、
飼い主の方と相談の上、膀胱結石だけ取る手術を行うことになりました。
(実際、手術までの2~3日間は調子が良かったのですが、
手術当日にまた尿道に詰まった状態になってしまいました)
手術は麻酔の量を少しでも減らすため、
また体への負担を少しでも減らすため、
何種類かの鎮静剤や鎮痛剤を組み合わせて、
麻酔の量を減らしながら行いました。
慎重に麻酔をかけて、手術開始。おちんちんの横を切り、お腹をあけます。
そしてお腹を開けたら、膀胱を確認。
膀胱を体外へ少し引っ張り出し、膀胱に切開を加え、結石を取り出します。
膀胱を体外へ引っ張り出した様子です↓
結石の取り残しがないことを確認してから、膀胱をきれいに縫い、
おなかを閉じて手術終了。
ところで膀胱に限らずですが、縫うときはその間隔が重要です。
膀胱の切開した部位から尿が漏れては大変ですので、
縫う間隔を狭くして、きつく縫う印象を持つかもしれませんが、
そうすると血液の流れが悪くなるため傷口がくっつきません。
しかしあまりに間隔をあけて縫いすぎても当然だめです。
適度に間隔をあけて、血液の流れを邪魔しないようにしないといけません。
傷口を治すためには血行が重要です。
話が少し逸れましたが、
摘出した膀胱結石の写真です。
その数、大小合わせ130個以上!!
(途中まで数えていたのですが、小さいものもたくさんあり、
数えきれなくなりました・・・)
手術翌日は体調が悪そうな様子もあったのですが、
翌日の夜には食欲旺盛に。
(もともと大食漢だそうです )
)
手術後4日間ほど入院しましたが、
今は退院して自宅で落ち着いて過ごしていますが、
まだ手術後のケアと結石予防の治療を行っていかなくてはなりません。
膀胱結石はある程度予防できる面もありますので、
今後はそちらの話もさせて頂きますね。
2012年09月16日
食べてはいけないもの
人間も動物も食欲があるということはいいことですが、
人間は大丈夫でもワンちゃんや猫ちゃんは食べてはいけないものが沢山あります。
一般的に知られているものとしてはタマネギでしょうか。
タマネギに限らず、ネギ類・ニンニクはワンちゃん猫ちゃんが食べると、
血液の中の赤血球が酸化されて、溶血といい、赤血球が溶けてしまいます。
すると赤黒い尿が出て、貧血になってしまいます。
タマネギを食べてしまい症状が出た場合には、点滴や抗酸化剤の投与、
ひどい場合には輸血が必要になりますが、
一番大事なのは食べてしまわないように注意することですよね。
またチョコレートもダメ、ということを知っている方も多いかと思います。
チョコレートの中のテオブロミン、という成分がよくないのですが、
チョコレートだけではなく、ココアやコーヒーもダメです。
このテオブロミン、甘いチョコレートには少なく、苦いチョコレートに多く含まれています。
なら甘いチョコレートなら大丈夫?、というわけではありませんので、チョコレートも控えて下さいね。
またチョコレートの場合脂肪分が多いため、
膵炎を引き起こすこともありますので、そういった面からも注意が必要です。
ブドウ・レーズンも腎不全を引き起こすことがあるため、基本的には与えてはいけません。
ただし、ブドウやレーズンの場合は中毒成分がまだ特定されているわけではありませんので、
腎不全になってしまうメカニズムが不明です。
食べ物ではありませんが、植物のユリも腎不全を引き起こすことがあります。
極端な例だと、花粉を少しなめただけで重度の腎不全になってしまった猫ちゃんもいるようです。
腎不全は命にかかわる重大な疾患ですので、
ブドウやユリには動物を近づけないようにして下さいね。
意外なものではマカダミアナッツ、これも中毒を引き起こし神経の機能に異常が出て、
震えや痙攣などを引き起こします。死亡例もあるそうです。
僕が今まで診察した中で印象深い子が、
パグの子でマカダミアナッツを食べてしまった子です。
フラフラしてまっすぐ歩けず、
突然前足2本で体を支えるような様子になってしまった子がいました。
ちょうどカエル倒立のような様子ですね。
ワンちゃんであのような態勢は衝撃的でしたが、治療への反応も良くすぐに改善しました。
キシリトールもよくありませんよ。
食べても平気な子もいるのですが、
中毒を起こし、血糖値が下がってしまう子もいます。
重篤な場合には肝不全にまでなってしまうワンちゃんもいますので、注意して下さい。
またユリと同様食べ物ではありませんが、クワズイモ。
部屋に飾ってある方もいるかもしれませんが、これもダメです。
クワズイモの語源は、食べられない(=クワズ)イモ、だそうです。
クワズイモの場合、中毒とは異なりますが、
シュウ酸カルシウムという成分が含まれています。
このシュウ酸カルシウム、顕微鏡で見るとトゲトゲしているそうで、
口に入れてしまうと口や食道粘膜・胃粘膜に刺激が加わり、
しびれや嘔吐が出るようです。
クワズイモに関しては、動物だけではなく人間でも同じ症状が出るようですよ。
その他にも色々とあるのですが、きりがないですので、今回はここまでで。
また少しずつこのような情報も載せていきますね。
2012年09月14日
ワンちゃんの去勢手術
ワンちゃんの去勢手術を行った時のことです。
「あれ? 残ってる!?」 との言葉が印象に残りました。
どういうことかというと、通常ワンちゃん・ネコちゃんの去勢手術は、
精巣だけを取り、おちんちん自体は取りません。
この飼い主さんはおちんちんも取ってしまう手術だと思っていたのです。
手術の説明時に「精巣を取りますよ」とは伝えているのですが、
たしかに一般の方にはわかりにくいですよね・・・。
説明はわかりやすく、と心がけているのですが、反省しました。
通常の去勢手術は、下の写真のように精巣だけを取る手術になります。
(精巣を体外へ引っ張り出し、精巣の血管と精管を縛っているところです。
この後、精巣だけを摘出します)

去勢手術の時期ですが、生後半年以上であればいつでも構いません。
もちろん去勢手術によるメリット・デメリットがありますので、
それも含め去勢手術を行うかどうか考えてもらえればいいのですが、
メリットとして、発情が来なくなる(=発情時の興奮がなくなる)、
精巣の病気がなくなる、ことが挙げられます。
また若いうちに去勢手術をしておけば、
かなりの確率で男性ホルモンに起因する病気も防ぐことができます。
デメリットの一番大きなものは太りやすくなるということでしょう。
そうなる子もいるのですが、元来の性格の関与が強く、
去勢手術だけで抑えられるものではないのです。
また若いうちに去勢手術をすればマーキングも減りますが、
余談ですが、ニホンザルなどでは精巣をとる手術ではなく、
精管だけを縛る手術が行われることもあるそうです。
なぜかというと、これ以上繁殖しては困るけど、
オスとしての威厳や気質は残しておきたい、という目的があるそうで、
その場合に精管を縛ってしまう手術が行われることもあるそうです。
精管とは精液の通り道ですので、これを縛ってしまえば繁殖することはありません。
しかし精巣自体は残っていますので、男性ホルモンは出るため、
オスとしての行動は変化がないそうですよ。
(ちなみに、精巣は精液や男性ホルモンを作る臓器、
精管は精液の通り道、精液は精子を含む液体です。
精管・精巣・精液・・・、やっぱり説明って難しい・・・)
2012年09月11日
自宅でのシャンプーの仕方
皮膚・被毛のケアの為にはシャンプーは必要ですし、
やはり臭いも違ってきます。
今回は自宅でのシャンプーの仕方について、
お話させて頂きます。
よく飼い主様とシャンプーについて話していると、
ドライヤーで乾かしている、という方が多いのですが、
これは注意が必要です。
ドライヤーが悪いというのではなく、
大事な点は「温度」です。
ドライヤーだけではなく、お湯も温度が重要です。
ドライヤーは「冷風」が基本、体を洗うお湯は「ぬるま湯」もしくは「水」です。
(もちろん、時期や環境にもよりますよ。
寒い時期に外で水や冷風だけでのシャンプーは控えて下さいね)
では順を追って説明しますね。
なお今回はあくまで一般的なシャンプーの話です。
薬用シャンプーでは種類により多少異なることがありますので、
その辺りは病院でご質問下さい。
①水もしくはぬるま湯で体を十分に湿らせます。「十分に」が大切です。
体に付着した埃などもここで一緒に洗い流しましょう。
水だけならば、多少顔にかかっても、耳に入っても通常は問題ありません。
②シャンプーを手に取り、しっかりと泡を立ててから、その泡で体を包み込むように、
優しく皮膚と被毛をマッサージします。
もしくは小さな容器にぬるま湯とシャンプーを入れて、そこでシャンプーを泡立ててから
体を洗ってもいいですね。
シャンプーの原液をそのまま体にかけて、体で泡立たせるのはやめて下さい。
なおシャンプーが眼に入った場合には十分水で洗い流してあげて下さい。
③ぬるま湯もしくは水で、十分体についたシャンプーを洗い流します。
ここでも「十分に」洗い流して下さいね。
④タオルで体をしっかりとふきます。
ゴシゴシとこするというよりも、あくまで水分をしっかりと吸い取るという気持ちです。
何枚かタオルを代えて、十分水分を取り除いて下さい。
可能ならば、タオルだけでの乾燥でもOKですが、相当時間がかかります・・・。
現実的には、殆どの場合はドライヤーが必要でしょう。
⑤ドライヤーで乾かします。十分乾かすことが大切です。
温風ではなく、冷風が理想的です。
もし温風でやるのであれば、体からドライヤーまでの距離を離して、
皮膚が熱くならないように気をつけて下さい。
皮膚が暑くなると痒みが出やすくなりますし、
皮膚が熱を持つと必要な水分までも奪われてしまい、
カサカサしたり、皮脂が出やすくなりますよ。
また乾燥が不十分だと、毛玉や湿疹ができやすくなります。
⑦必要に応じてですが、保湿剤などのコンディショナーを使用して終了です。
よく質問されるのがシャンプーはどのくらいの頻度で行えばいいんでしょうか?
ということです。
ワンちゃんにより多少異なりますが、週に1回であればやり過ぎなことはありません。
ただ皮膚の状態が落ち着いている子であれば、月に1回でも十分です。
その辺りは皮膚の状態や臭いを加味して調整する必要があります。
以上、簡単でしたが、今回はシャンプーの仕方でした。
不明点・判らないことがあれば、ご質問下さいね。
2012年09月07日
耳を咬まれてしまったワンちゃん
病院に来たときは元気でしたが、耳はかなり大きな傷がありました。
耳の外側は縦数センチ程裂けてしまい、
耳の内側はV字型に裂けていて、傷は貫通してしまっていました。
耳の中には軟骨が入っているのですが、その軟骨ごと裂けてしまっていたのです。
一般的には咬まれてしまった場合の治療として、
①傷を縫う治療、②傷を縫わない治療に分かれます。
②の傷を縫わないというのは、
傷を縫ってもその中にばい菌を閉じ込めてしまい、
一見治ったように見えても傷の下で化膿してしまうことがあるため、
あえて縫わずに傷を開けたままの状態にして(開放創といいます)治療する方法
です。
しかし今回の場合は、傷がかなり大きく、軟骨まで裂けてしまったため、
傷を縫うことにしました。
動物の場合、
デリケートな縫合が必要な場合は
動かないようにしないといけませんので、麻酔が必要
です。
このラブちゃんもまず
身体検査・血液検査で大きな問題がないことを確認してから、
全身麻酔をかけて傷の処置を行いました。
麻酔下で毛刈りをして十分な洗浄・消毒を行い、
汚れてしまった組織を少し取り除き(デブリードといいます)、
傷がくっつきやすいように傷口の形を整えました。
その後、軟骨と皮膚を寄せて、縫い合わせます。
こちらがその様子です↓
麻酔から目覚めるのはとても早く、
飼い主さんがお迎えに来た時にはラブちゃん大喜びでした。
抗生剤はしばらく飲むことになるでしょうが、
化膿しないで治ってくれるといいですね。
楽しいひと時が、ちょっと残念なことになってしまったラブちゃんでした。