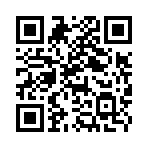2013年05月30日
子宮蓄膿症という病気
ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。
今回は子宮蓄膿症という病気についてです。
病名の通り、
子宮の中に膿が貯まってしまう(蓄膿)病気で、
治療をしないと生命に関わる、重大な病気です。
猫ちゃんでもみられますが、圧倒的にワンちゃんに多い病気で,
また時期も関係があり、
発情の出血があった後、1~2か月後に発生することが多い病気です。
ですので、今の時期は比較的この病気が多くなりますが、
必ずしも発情出血の後だけに発生するわけではありません。
発情の後、偽妊娠をするワンちゃんが時折います。
この場合、妊娠はしていないのに、
妊娠した時と同じように卵巣に黄体というものができ、
その黄体からのホルモンの影響で、
あたかも妊娠しているかのように乳腺が腫れて、
またミルクが出ることもあります。
その偽妊娠の時期になると、
子宮の中の抵抗力が落ちるため、
外陰部からの細菌感染を起こしやすくなります。
それが悪化すると、子宮の中で重度の細菌感染が起き、
その結果膿が貯まって子宮蓄膿症という病気になります。
避妊手術をしていないワンちゃんで、
7~8歳を過ぎると発生率が増加します。
治療は
①手術(卵巣と膿の貯まった子宮を摘出します)、
②ホルモン剤での治療、
③抗生剤での治療、
などがありますが、
③の抗生剤での治療はほとんどの場合うまくいきません。
まれに改善したとしてもすぐに再発してしまうことが殆どです。
また②のホルモン剤の治療の場合、一時的には改善することが多いのですが、
やはり再発の可能性が十分あります。
これは子宮の感染だけがこの病気の原因ではなく、
ホルモンの乱れが関係しているためです。
このホルモンというのは卵巣から出るホルモン(とくに黄体から出るホルモン)です。
つまり子宮が一度改善しても卵巣からのホルモンの問題で、
また子宮にトラブルが起きてしまうことになります。
ですので、
卵巣と膿の貯留した子宮を摘出すること①の手術が望ましく、
手術が無事終われば再発は無くなります。
この子宮蓄膿症では、わかりやすい症状として外陰部から膿が出る場合があります。
下の写真のように外陰部から膿が出ている場合は、
ほとんどの場合がこの子宮蓄膿症と言う病気です。
その他には、
水をたくさん飲んでおしっこをたくさんする(多飲多尿)場合や、
元気がなくなる、下痢や嘔吐、食欲不振などの症状
が出ることもあります。
下の写真は5歳のトイ・プードルの子の手術中の写真です。
食欲が1週間ほどないとのことで検査したところ、子宮蓄膿症でした。
翌日に手術をして、2泊入院して元気に退院しましたが、
この子の場合、体重2.6kgなのに、摘出した子宮の重さは200g。
体の8%ほど、60kgの人間だと5kgほどの重さの子宮が体の中に入っていたことになります。